現代の営業現場では、業績向上を目指して各企業が努力を重ねている一方で、「営業のサボり」という問題が顕在化しています。外回り営業を任される社員が、実際には仕事を怠けたり、成果を上げずに時間を浪費しているケースは少なくありません。この問題が続くと、会社の売上に直接的な影響を与え、チーム全体の士気低下にもつながります。
本記事では、営業がサボる原因やその心理を掘り下げ、対策や解決方法を詳しく解説していきます。営業部門の健全な業務運営を目指すために、まずはサボりの原因を理解し、その対処法を見出すことが重要です。
営業がサボる原因と心理
営業マンがサボる背景には、さまざまな心理的要因や環境的な要因が絡んでいます。以下に、主な原因をいくつか挙げて解説します。
サボり癖がついている
営業マンがサボる原因のひとつに、「サボり癖」があります。これは、長期間にわたって業務を怠ける習慣がついてしまい、何かしらの適当な理由で仕事をサボることが当たり前になっている状態です。初期段階では小さなサボりでも、それが繰り返されるうちに習慣化し、本人にとっては「問題ではない」と感じるようになってしまいます。この心理状態では、周囲の目を気にせず、自己正当化をすることもあり、上司が気づかない限り改善されにくい状況です。
仕事にやる気がない
仕事そのものに対する興味や情熱を失った営業マンは、サボりがちになります。彼らは業務に対して真剣に取り組むことができず、時間を無駄にしてしまうことが多いです。やる気がない原因としては、自己成長を感じられない、目標が曖昧でモチベーションが保てないといったことが挙げられます。営業活動が単調なルーチンワークのように感じられると、モチベーションが下がり、結果的にサボる傾向が強くなるのです。
プレッシャーがかかりすぎている
営業は常に結果が求められる職種であるため、時に過度なプレッシャーがかかることがあります。高すぎる目標や上司からの圧力が続くと、営業マンは精神的に疲弊し、動けなくなることが少なくありません。このような状況では、「どうせ達成できない」と感じ、サボりや怠慢につながることがあります。過度のプレッシャーは、やる気を削ぐだけでなく、営業マンのストレスを増大させ、業務パフォーマンスを大きく低下させます。
商材や会社への不信感
営業マンが取り扱う商材や会社の方針に対して信頼が持てない場合も、サボりの要因となります。例えば、商材自体に自信が持てず、お客様に対して自信を持って提案できない場合、営業活動が消極的になりがちです。また、会社のビジョンや方針に対する不信感や不満があると、営業マンは心のどこかで「会社のために頑張る意味がない」と感じ、サボるようになります。商材や会社に対する信頼感が欠けていると、営業活動全体に悪影響を及ぼします。
結果が出ず、モチベーションが低下
営業マンが一定期間努力をしても成果が出ない場合、やる気を失うことは珍しくありません。特に、目標に到達できない日々が続くと、「自分には向いていない」「何をやっても無駄だ」と感じ、結果的に仕事に対する熱意が失われます。このような状況では、サボりに走ることが多く、他の活動や無駄な時間に逃避する傾向があります。モチベーションが低下した営業マンは、自己改善や努力を怠りがちになり、そのまま成果を追い求める意欲を失うのです。
サボりがちな営業マンの特徴
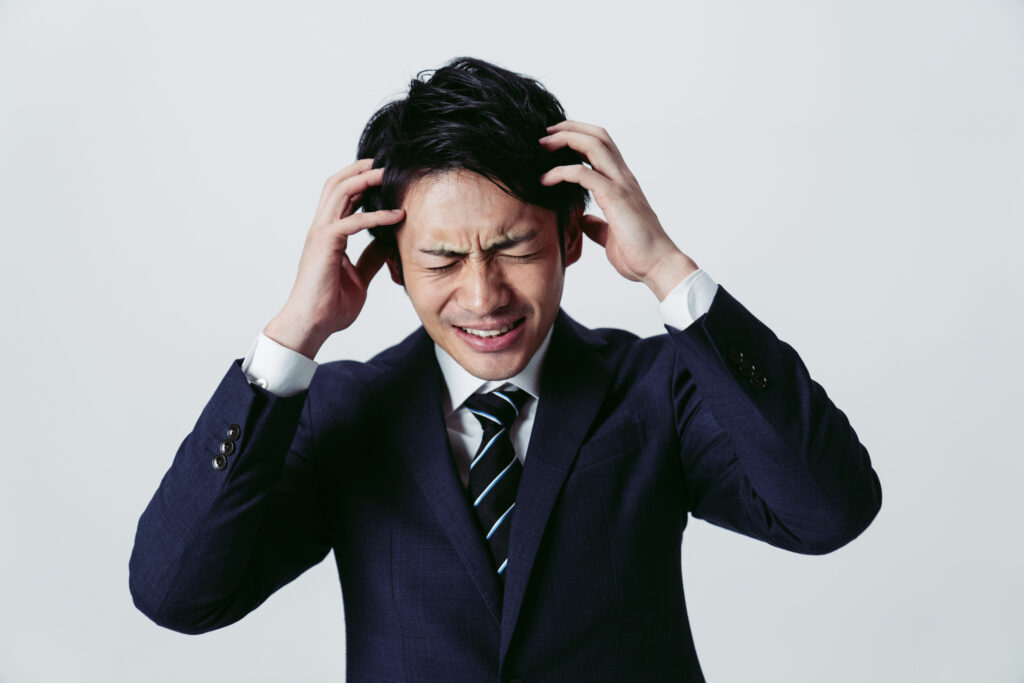
営業マンがサボっているかどうかを見極めるのは難しい場合もありますが、いくつかの共通する特徴があります。これらの特徴に気づくことで、早期に対策を講じ、改善のためのアプローチを取ることが可能です。
外出が多い割に成果が上がらない
営業職では外出が多く、クライアントとの直接対話が仕事の重要な部分を占めます。しかし、サボりがちな営業マンは頻繁に外出しているにもかかわらず、成果が上がっていないことが特徴的です。顧客訪問の数や時間だけを見れば「熱心に働いている」と思えるかもしれませんが、実際にはクライアントとの商談がうまくいっていない、あるいは外出の大半が実質的な営業活動ではないというケースもあります。このような場合、訪問記録や営業日報を詳細に確認し、どれだけ有効な活動が行われているのかを分析する必要があります。
報告・連絡・相談が少ない
営業活動において、「報告・連絡・相談」(いわゆる「報連相」)は非常に重要です。サボりがちな営業マンは、こうした基本的なコミュニケーションが疎かになる傾向があります。例えば、定期的な進捗報告を怠ったり、必要な連絡をせずに物事を自己判断で進めてしまうことが見られます。この「報連相」が不足している場合、営業の実態が見えにくくなるため、上司が営業マンの業務状況を正確に把握することが困難になります。また、相談をしないことで問題を抱え込んでしまい、結果的に成果が上がらないままサボりに走るケースも少なくありません。
社内での仕事は熱心だが外回りで成果が出ない
社内にいる間は熱心に業務を行っているように見えるものの、実際に外部での営業活動が疎かになっているケースもサボりの特徴です。たとえば、デスクワークや社内会議には積極的に参加し、周囲からは「働いている」という印象を与えますが、実際には外回りでクライアントと会う時間を減らしていたり、訪問先での成果が出ていないことがよくあります。このタイプの営業マンは、表面的には忙しく見えるためサボりが指摘されにくいものの、最終的な売上や契約数に結びつかない場合が多いです。このような状況では、社内での評価が高くとも、外回りでの成果をしっかりと確認する必要があります。
これらの特徴が見られる営業マンに対しては、営業活動の効率を見直し、明確なフィードバックや目標設定を行うことが必要です。定期的な進捗管理を徹底し、サボりを防ぐ環境づくりが重要になります。
サボりがちな営業マンへの対応策
営業マンがサボることによる影響は、業績やチーム全体の士気に悪影響を及ぼします。サボりを発見した場合は、適切な対応を取ることが重要です。以下では、サボりがちな営業マンへの具体的な対応策をいくつかご紹介します。
事実確認を行う
まず、営業マンが本当にサボっているのか、客観的な事実確認を行うことが必要です。上司としては、ただの憶測や感情で判断せず、データや証拠をもとに状況を正確に把握することが肝心です。たとえば、訪問記録や営業活動の報告書、クライアントからのフィードバックなどを確認し、業務内容に不自然な点がないかをチェックします。営業マン自身も状況を正確に把握するためにヒアリングを行い、事実に基づいて現実的な対応を進めることが求められます。
根拠をもとに注意する
サボりが確認された場合、感情的に叱るのではなく、明確な根拠をもとに冷静に指導することが大切です。例えば、「何時から何時までの訪問予定が記録されていない」「クライアントからの対応が遅れている」といった具体的な例を示すことで、営業マンに自分の行動を認識させることができます。事実に基づいたフィードバックを行うことで、営業マンに自らの行動を見直させ、改善を促す効果的なアプローチが可能です。また、今後の改善策や期待する行動を明確に伝え、次のステップを示すことも重要となってきます。
営業支援ツールやGPSで監視する
最近では、営業マンの活動を可視化するための営業支援ツールやGPSを活用する企業が増えています。これらのツールを導入することで、営業の行動パターンをリアルタイムで把握でき、無駄な時間を減らすことができます。たとえば、訪問先や移動時間が正確に記録されるため、営業マンの動きが透明化され、サボりが難しくなります。また、こうしたツールを使うことで、サボりを防止するだけでなく、業務効率の向上や適切なフィードバックが可能になるため、営業活動全体の改善にもつながります。
チームでの役割を与える
営業マンが個人プレーに走りがちな場合、チームでの役割を与えることは効果的な対策の一つです。営業活動は個人の成果が重視されますが、チーム全体としての目標を持たせ、各メンバーに責任感を持たせることで、サボる余地を減らすことができます。例えば、営業チームの中でのリーダーシップ役や、特定のプロジェクトを任せるといった形で役割を持たせることで、他のメンバーの期待も背負い、より真剣に業務に取り組むことが期待されます。チームプレーの一体感が強まることで、自然とサボりづらい環境が形成されます。
先輩営業との同行を増やす
営業のサボりを防止するために、先輩営業マンと同行させることも有効な方法です。ベテランの営業マンと行動を共にすることで、営業のノウハウを学ぶと同時に、仕事に対する意識を引き上げることが期待されます。また、先輩の成功事例や営業スキルを間近で見ることで、自分の営業スタイルに自信を持つことができ、モチベーション向上にもつながります。特に、新人や成果が出ない営業マンにとっては、同行を通じて実践的な学びを得る機会となり、サボる時間が減少するだけでなく、スキルアップにもつながるでしょう。
これらの対応策を実行することで、サボりがちな営業マンの行動改善を促し、チーム全体のパフォーマンス向上を図ることができます。
サボりにくい環境づくり
営業マンがサボらずに効率的に業務を進められる環境を作ることは、会社全体の成果向上に直結します。サボりを未然に防ぐためには、組織としての制度やサポートが重要です。ここでは、サボりにくい環境を整えるための具体的な施策を解説します。
定期的な報告制度の導入
営業マンの進捗を可視化し、サボりを防止するために、定期的な報告制度を導入することは非常に有効です。例えば、毎週または毎月の進捗ミーティングを設定し、個々の営業マンが現在の成果や課題をチーム全体で共有する機会を設けることで、業務の透明性を確保します。報告の場を定期的に設けることで、上司は各営業マンがどのように業務に取り組んでいるかを正確に把握でき、サボりを早期に発見することが可能です。また、営業活動の進捗をリアルタイムで把握するために、CRM(顧客関係管理)システムや営業管理ツールを活用し、報告内容を効率化することも効果的です。これにより、営業マンは自身の活動を振り返る機会を得て、次の行動計画を明確にすることができます。
成果の可視化と適切な評価
営業マンの努力や成果を公正に評価するためには、成果を数値化し、可視化することが重要です。成果の可視化とは、売上、契約件数、新規顧客の獲得数などを具体的な数値で示し、誰がどれだけの成果を上げたのかを明確にすることです。このようなデータを共有することで、各営業マンは自分の立ち位置を把握し、次に目指すべき目標が明確になります。さらに、適切なフィードバックと評価を行うことで、営業マンのモチベーションを維持することができます。例えば、成果が上がっている営業マンには具体的な褒め言葉やボーナスを提供し、さらに努力を続けられるようサポートします。一方、成果が低迷している営業マンには、改善点を具体的に指摘し、建設的なアドバイスを与えることで、次に繋がる行動を促します。このようなフィードバックのサイクルを確立することで、営業マンは自分の成長や貢献度を実感でき、サボりにくい環境が整います。
モチベーション向上のための施策
営業マンが仕事に意欲を持ち続けるためには、定期的にモチベーションを高める施策を実施することが効果的です。まず、インセンティブ制度を導入することで、営業マンに対して成果に応じた報酬を提供します。例えば、売上目標を達成した際にボーナスを支給したり、成績優秀者に対して表彰制度を設けることで、さらなる努力を促すことができます。また、キャリアアップの機会を提供することも、営業マンのモチベーションを高める上で重要です。昇進や新しいプロジェクトへの参加機会を与えることで、営業マンは自己成長の可能性を感じ、日々の業務に意欲的に取り組むようになります。さらに、定期的なトレーニングやスキルアップの機会を提供することも、営業マンが仕事に対して前向きな姿勢を維持するために有効です。モチベーションを高める施策を複数組み合わせることで、営業マンが目標に向かって努力を続けやすい環境を整えることができます。
これらの施策を適切に導入することで、営業マンが自主的に働く意欲を持ち、サボりにくい環境を作り上げることが可能です。環境づくりに重点を置くことで、長期的に高い成果を期待できるチームへと成長させることができるでしょう。
営業代行の活用

営業マンのサボりや業績不振を解決するための一つの手段として、「営業代行」の活用があります。営業代行とは、外部の専門業者に営業活動の一部または全てを委託するサービスです。これにより、社内リソースを効率的に使いながら、営業成果を向上させることができます。ここでは、営業代行のメリットや導入方法について詳しく解説します。
営業代行のメリット
営業代行を活用することで、企業は複数のメリットを享受できます。
1. 即戦力の確保
営業代行会社には、豊富な経験と専門知識を持ったプロの営業スタッフが在籍しており、すぐに戦力として活躍してくれます。新たに営業マンを採用して教育する手間や時間を省けるため、短期間で結果を出したい企業にとって非常に効果的です。特に、新規開拓が急務の状況や、新しい市場に参入する場合などで大きな成果が期待できます。
2. コスト削減
営業活動を自社で行う場合、採用、トレーニング、人件費など、多くのコストがかかります。一方で、営業代行を利用することで、これらのコストを削減できます。営業代行は、契約期間や業務内容に応じて費用を調整できるため、固定費としての負担を抑えることが可能です。また、営業代行は成果報酬型の料金体系を採用している場合も多く、企業は成果に応じた支払いを行うだけで済むため、コストパフォーマンスが高いのが特徴です。
3. 専門知識やノウハウの活用
営業代行会社は、特定の業界やターゲットに対する深い理解と、豊富な営業ノウハウを持っています。そのため、営業代行を活用することで、企業は最新の営業手法や効率的な営業プロセスを導入することができます。これにより、自社の営業チームが学ぶべき知識や技術をすぐに取り入れ、競争力を高めることができます。
営業代行会社の選び方
営業代行を導入する際には、信頼できる営業代行会社を選ぶことが成功の鍵となります。以下のポイントを基準に、適切なパートナーを選定しましょう。
1. 実績
まず、営業代行会社の実績を確認することが重要です。過去にどのような企業と取引があったか、どの業界に強みがあるか、そして実際にどれくらいの成果を上げているかをチェックしましょう。実績が豊富な会社ほど、信頼性が高く、業界に応じた効果的な営業戦略を持っている可能性が高いです。
2. サービス内容
営業代行会社は、提供するサービスの範囲が異なることが多いです。たとえば、テレマーケティングやフィールドセールス、新規顧客開拓など、どのような営業活動を代行できるかを確認しましょう。自社が抱える課題に応じて、最適なサービスを提供できる会社を選ぶことが大切です。また、営業代行が単なる業務代行だけでなく、マーケティング戦略や顧客管理のサポートも行っているかを確認すると良いでしょう。
3. 費用
営業代行の費用は、企業の規模や業務内容によって異なります。費用対効果を最大化するために、料金体系が明確であるか、予算に見合ったサービスが提供されるかを確認することが重要です。成果報酬型や月額固定型など、どのような料金モデルが採用されているかも選定のポイントになります。
営業代行導入の流れ
営業代行を導入する際のステップは比較的シンプルですが、効果を最大化するためには事前の準備が欠かせません。
1. 目標設定
まず、自社が営業代行に期待する成果や目標を明確にしましょう。新規顧客の獲得数、売上目標、リードジェネレーションの件数など、具体的な指標を設定することで、営業代行会社に求める成果を共有できます。
2. 営業代行会社との打ち合わせ
次に、営業代行会社と詳細な打ち合わせを行い、自社のニーズに応じたプランを策定します。この際、自社の業界特性やターゲット市場、現在の課題などを正確に伝えることが重要です。双方の合意のもとで、実際の営業活動の範囲や内容が決定されます。
3. 業務開始とモニタリング
営業代行の業務がスタートしたら、定期的なモニタリングを行い、進捗状況を確認します。代行業務の成果を数値で評価し、必要に応じて調整を行うことで、効率的な営業活動が維持されます。また、営業代行会社との連携を密に保つことで、改善点を共有し、継続的な成果向上を目指します。
まとめ
営業マンのサボりに対する対応策や環境改善は、長期的な業績向上に不可欠です。しかし、すべてを社内で賄うことが難しい場合には、営業代行の活用が効果的な解決策となります。営業代行を活用することで、即戦力を確保し、コストを削減しながら、専門的な知識やノウハウを活用することが可能です。また、適切な営業代行会社を選び、効率的に運用することで、営業活動全体の改善が期待できます。サボりの問題を解決し、営業効率を向上させるために、営業代行は強力なパートナーとなるでしょう。
ネオクリエイトでは企業の問題やターゲットに併せたご提案が可能です。営業経験豊富な人材による営業活動で更なる成果が期待できます。
営業にお悩みの企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。









